マートンの人生
1944年アメリカのニューヨーク市マンハッタンで生まれた。父親は有名な社会学者ロバート・キング・マートン。(本稿の人物はロバート・コックス・マートン)
コロンビア大学、カリフォルニア工科大学で数学を学んだ後に、博士課程ではマサチューセッツ工科大学(MIT)で経済学を学んだ。そこでポール・サミュエルソンの数理経済学コースに参加することになりる。
1969年にはオプション価格理論の研究でフォッカープランク方程式を使用するなど高度な数学を熟知していた。
1970年からMITで研究をするようになると、隣の部屋で研究をしていたマイロン・ショールズと共同で研究をするようになる。
同時期にショールズと共同研究をしていたフィッシャー・ブラックとも共同で研究をするようになる。
こうして3人で協力して研究をすすめ、ブラックショールズモデルを完成させる。
ブラックショールズモデル完成に至るまでにマートンが果たした役割は「確率微分を用いたこと」である。ブラックとショールズが離散時間で理論を展開し、その後にマートンが確率微分を用いて連続時間に変換した。
実はマートンとサミュエルソンは1969年時点でブラックショールズモデルと同様の形式の公式にたどり着いていましたが、インプットとして原資産の期待収益率がどうしても必要だった。
ブラックとショールズとともに原資産の期待収益率を必要としないブラックショールズモデル導くことができ、「完璧な一般均衡理論」の形式であると述べている。
株式固有の(リスク選好や総供給に依存した)期待収益率から離れることができなかった。しかし、ブラックとショールズのアプローチでは、市場の無リスク金利とボラティリティのみのインプットが必要なだけであり、そこではCAPMのβ(つまりその株式固有の期待収益率)の入力は必要とされていない。マートンはこの点によってブラック・ショールズ・モデルは「完璧な一般均衡理論」の形式を持った方法であり、成功(ブレーク)する可能性があると指摘している。
数理ファイナンスの歴史 - 櫻井 豊
1974年にはブラックショールズモデルの枠組みを使用して倒産確率を推定することを試みます。これはのちにマートンモデルと呼ばれ、構造モデルの代表的なモデルとして使用されることになる。
1988年からはハーバード大学で教鞭をとり、1997年にはショールズとともにノーベル経済学賞を受賞することになる。授賞理由は「a new method to determine the value of derivatives」である。
1994年にはショールズとともにヘッジファンドであるロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)の創業メンバーになり、LTCMは驚異的な運用成績を残した。しかし、1997年に発生したアジア通貨危機、1998年のロシア財政危機の影響で巨額な損失を抱え倒産した。
ノーベル経済学賞受賞者2名が関与しているヘッジファンドが破綻したことで、ノーベル経済学賞や金融工学に対して世間から疑問の声が上がるようになった。
2010年からはMITスローンで教鞭をとっている。
マートンモデル
1974年に発表した『On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates』で取り扱っているモデルはマートンモデルと呼ばれている。倒産確率を推定するモデルで構造モデルの代表的なモデルである。
倒産確率を推定するモデルは以下の3つに大別される。
- 統計モデル
- 構造モデル
- 誘導モデル
統計モデル
回帰式など統計学的なアプローチを用いるモデル
- アルトマンのZスコア
構造モデル
バランスシートを用いるモデル
- マートンモデル
- ブラックコックスモデル
- KMVモデル
誘導モデル
ハザードレートを用いるモデル
- ダフィーシングルトンモデル
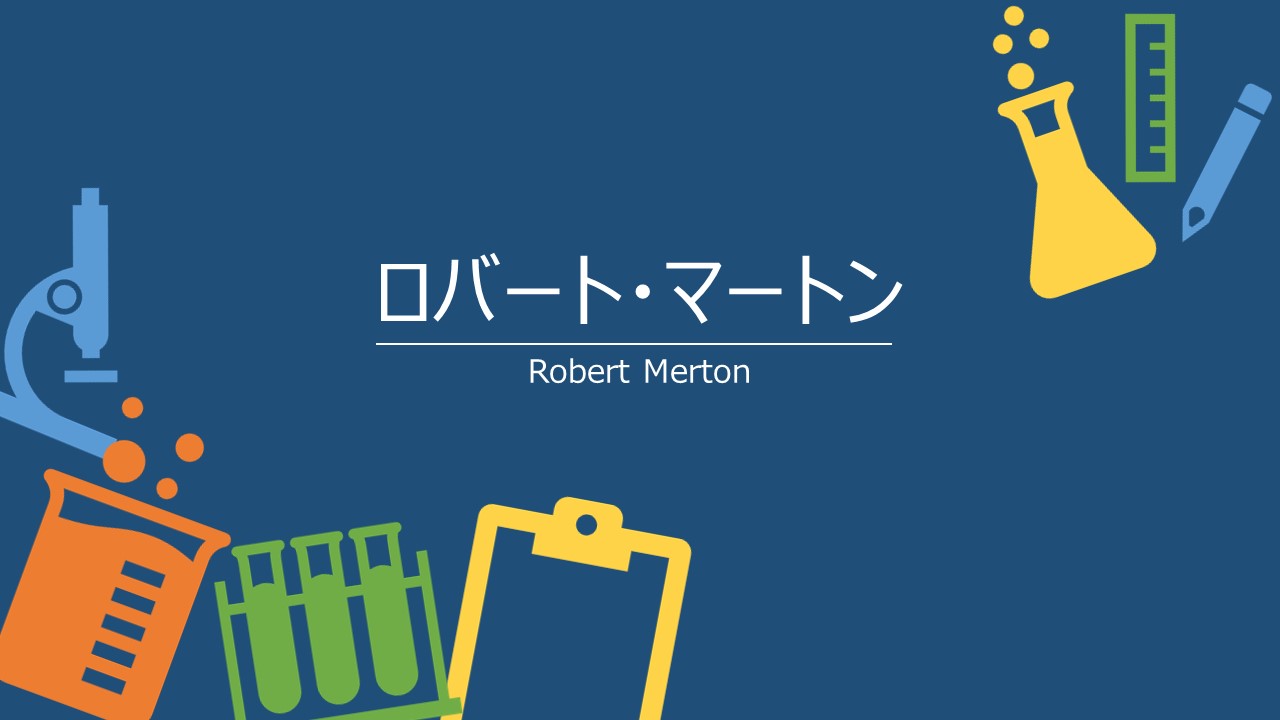




コメント